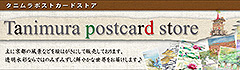プロフィール
 2013/05/03 更新
2013/05/03 更新
「ランドスケープアート」にお越しいただきありがとうございます。
美術の学校へ行くこともなく、造園会社に勤めながら京都各地を水彩画で手軽にスケッチしておりましたものをこのサイトに載せたのが始まりでした。現在は独立開業しておりますが、相変わらず好きな絵を描いていることには変わりありません。美術会に所属し出品したり、教室を開くなど、活動の幅は広がってきております。
谷村 勲
2001年
環境建築デザインコンペティション 佳作 京の新しいすまい (京都府建築士会)
2002年 札幌国際デザイン賞 入選 札幌の新しいライフスタイルをデザインする
2003年 京都景観・まちづくり賞 優秀賞 桜井公園整備 (公園設計・まちづくり業務)
2004年 全国都市緑化おおさかフェア自治体出展「ふるさと花回廊」 京都府ブースデザイン
2005年 アートクラフトフェスタなどのイベントで絵はがきを販売する
2006年 京福電鉄嵐山駅横のごふくいしかわの店舗で絵はがきを委託販売
2007年 初個展、昭和美術会展に水彩画が2点入選
2008年 昭和美術会同人会員となる。第2回個展
2009年 水彩画の教室を開く、文人連盟所属、第3回個展
2010年
造園管理・設計・施工を行う、谷村庭園を独立開業
2012年
祇園祭うちわの水彩画製作(日立製作所)
結局は同じことをしています。
美大を目指してデッサンを習いに行った先で、教えてもらっていた講師の方が本業と別で教室をしていて、採算はあまり考えず続けていると話を聞き、
現実にはいくら絵がうまくなっても美大を出たところでやりたい仕事などそう就けるものではないと言われたこともあり美大ではなく、現実的に生活することを主にしつつも美的なセンスも生かせそうな工学部の建築を志望しました。ですが最終的な職業は造園です。仕事をしながらも好きな絵描きはずっとつづけてまいりましたが、独立開業(屋号をつけての活動は1年後)を機に趣味の延長で水彩画教室をはじめました。なにしろ独立当初は手伝い仕事が多少と自前の仕事はほぼ皆無に近い状況で、余りある時間を生かす手段のひとつとして教室を開いてみた訳です。教室は4年経って今年で5年目となり、造園業も去年からようやくと仕事も増えてきて軌道に乗りつつある状況となりました。
本業として造園が成り立ちつつあるなか、絵描きの活動は水彩画教室や年賀素材の製作とうちわの水彩画製作など、副業とまではいかないのですが小遣い稼ぎ程度の仕事となっています。生活を支えるとまでは行かない絵描きの活動はやはり趣味の延長ではありますが、好きなことですので辞めるつもりもありません。ここにきて美術を志した若かりし頃を思い出すようになり、影響はいまだに受け続けているのだと思うようになりました。教室を始める時もとりあえずやってみようか程度で始めた訳ですが、かつて影響はずっと無意識にはあったのかもしれません。反面教師と思っていたのに、なんの因果か結局は同じことをしています。
水彩画教室を始めて2年半経ちましたが・・・、
趣味が高じて始めてしまった水彩教室ですが、去年の暮れからようやく人が少し増えてまいりました。なんとか教室代など、運営費はまかなえるようになりましたが、まだまだ日当分としては寂しいものです。最初の1年目、京都教育文化センターでは、3ヶ月間、誰も人が来ません!
ドアのノックすらありません、静かな部屋で一人きりでした。 3ヶ月たって、1人の方だけ来て、以後、続けて熱心に来てくれております。その方が来ていなかったら1年目にして辞めていたとことでしょう。2年目からはアスニー山科へ移りましたが、
こちらも移って1年目は京都教育文化センターとほぼ同じ状況で、依然として1人の方だけは熱心に来てくれていて、
の他は、一人か二人方だけ3ヶ月程度来てもらえていたぐらいです。去年の秋・今年の春と、絵はがきを売りに行った際に、
大きめのちらしを配ったりと、地道で営業した結果、近場の方がなんとか少しづつ来てくれるようになりました。
こうしてようやくと、今年は常時1人という状況ではなくなりました! 趣味が高じた無名の画家では、教室にかかる諸経費の維持が関の山というのが現実というところですね。わかっていたことではあるのですが、やはり教室をしていても生活の足しとはなりません。でも、教える側となっていみて解った事が、自分自身が感覚で描いてきた色彩や技法、好んで使っていた色の特性などを、説明するために、具体的に意識するようになったことです。高校生の時にデッサンは習ったことはありましたが、水彩画は我流ですから、以前は技術的にこう描くとかあまり意識していなかったように思います。教える側に立ったので、自身の感覚を技術的なものとして意識するようになりました。そういうことで、教えることは、あまり意識にしていたの描くことの感覚を説明するために明確にしていく結果となりました。少ない人数ではありますが、なんとか経費がまかなえるようになっただけでもよかったです。今後もなんとか続けていけそうです。
自身にとって絵を描くということは、
小さい頃から絵を描くことは得意な方でした。ですが、特に好きかというと、実はそうでもなかったのです。小・中学校では美術時間となるといつもかなり描けていたもので、描き出すとかなり熱中しました。が、美術時間以外では絵を描くことは特にありませんでした。中学生まではそうしてこれといって絵に興味を持つこともなくすごしていたのですが、高校生の時に美術の時間に見た絵(中世ルネサンス絵画)にすごく衝撃を受け、それから強く美術に関心を持つようになりました。そこからようやくと自分で絵を描いてみたいと思うようになった訳ですが、高校入学時点で大学受験は工学部系と決めていたので、絵がうまいことは特に役にたたない!と思ってました。でも、役に立つ、たたない、そんなことは考えず、絵をやりたいのだから、美大を目指すことにしてデッサンを始めることにしたのです。美大受験の教室で1年弱デッサンを中心に習っておりましたが、単に絵を習うだけでなく、何人か教えにこられていた先生に自身の学歴や職歴、作品づくりなど生活や考え方までさまざまなことを聞きました。そこでは絵を習う以上に面白い話も聞けましたし、非常に厳しい現実との葛藤も教えてもらえました。美術では生活はできない・・・、そんなことは最初からわかっていたのですが、絵が好き=単純に美大に行きたいとの思いから、努力して相当な画力をつけることができれば将来の道も開けるのではないか、と思って習いに行っていましたが、先生達の話を聞いている内にだんだんと熱も冷めてしましました。結果的に言えば、美大受験を諦めさせるための教室?先生は実は反面教師だった(いい意味で)?といえるものでもありました。そもそも美大はお金もかかりますし、現実的に考えれば自ずと答えは出るのですが。でも、習いにいっていた間は集中してデッサンをしましたので絵画の基礎的な画力はその時にかなり身についたと思います。それで結局は、工学系大学で建築学科へ進むことにしました。建築には美術の要素もありますから、美大を諦めて建築を選んだという人も多くおられますし、自分自身もそうした道を選んだ訳です。芸術系大学の建築学科という手もありましたが、就職のことを考えれば工学部の方が有利ですから、芸術系の大学は外しました。それと仕事も早く経験したかったこともあり、大学は夜間のコースを選んでいます。それに夜間の方が学費も安いですから、昼間は設計事務所にバイトで行くようにして、学費は安上がりでバイト収入も得られて一石二鳥という訳です。でも夜遅くから課題など勉強して朝からバイトなので体力的には結構きつかったです。それでもせっかく習っていた絵を止めてしましたくなかったので、日曜日などの休みの日には京都の社寺仏閣などをスケッチしてました。そうして卒業後には建築設計事務所に勤めることになりましたが、建築設計業界は夜学生時代よりもハードで、給料は安い上に、毎日終電といった日々がずっと続き、本来休みの日も仕事があったりしますので、絵を描く時間はなくなってしまいました。このままこの仕事を続けることにも疑問に感じるようになり、せっかく大学の先生に紹介していただいて入った建築設計事務所でしたが、退職することを選択してしまいました。それで次の職としたのは日本庭園を海外でも多く手がけている造園会社でした。京都在住でしたから、小さな頃からお寺の境内でもよく遊んでいたので、そうした身近にあった寺院や庭園の関係で設計もできる仕事に携わりたいと都合のいいことを考えたのです。それがなんとも運よく京都でも数少ない造園コンサルタントに入社することができたのです。たまたま設計者の募集中に連絡したために、面接してもらえることになり、その際に今まで描いたデッサンやスケッチを見せたことで評価が得られた結果でした。役に立たないと思いながらも続けていた芸が身を助けたことになりました。その造園会社では数多くの公園・緑地設計や調査、造園工事を経験、造園技術と管理を学ぶことができ、絵が上手であることが認識されておりましたから、その能力を生かして仕事としてパース画もかなり描きました。趣味としてのスケッチ画とは違い仕事で描くとなるといろいろと社内外から細かい指摘や註文・変更があり大変ではありますが、それを何度も描いていると、要求に素早く答えるパース画も描けるようになっていきました。そうこうして描くことは仕事にもなっていったのですが、3年程前からは美術展への出品や個展を行うようにもなりました。これは趣味としてのスケッチは、作品性が少ないこと、実益としてのパース画は、依頼があって描くもので、自分の思うように描けないこと。ですので、自らの描くものに対して自分なりの作品性とか個性を出していきたい強く思うようになっていった訳です。最初から個性的な絵を描く方も多くおられるのですが、自分の場合は仕事として描くようになっていったことで、誰にでもわかりやすい綺麗な絵を描くことに意識が向いたように思います。わかりやすい綺麗な絵=独特な印象な少ない=個性的とはいえない=上手いだけなら誰が描いても同じではないか。と、そういうふうに思うようになり、このままの描き方でいいのか?人は自分の描いた絵に対してどう感じているのか?どう評価してくれるだろうかと?考えるようになりました。だから、それを確かめるために公募展への出品や個展と行うという行動へ向かうようになったのです。美術展では美術館という大きな展示空間で多くの絵と並べられます。自分の作品が他の人とどう違うのかがよくわかる場所でもあります。また自らの画力の程度も思い知らされる場所です。個展は自分の作品を一同に見てもらえます。そこで人に見てもらい、自分の絵がどのように見られているか、意見を聞くよい機会でもあります。美術展・個展共にでは多少に費用はかかりますが、こうした機会を持つことで作品は客観的に見えてくることになり、創作の刺激になり大きな意義のあるものです。絵が売れて採算がとれればいうことはありませんが、この不景気の現在においては望むべくもありません。そもそも仕事ではありませんし、自己満足のための行為でもありますから、経済的な回収はほとんど期待はできません。思えば、美大を目指した高校生のころには京都市美術館によく絵を見に行ってたものでした。当時の公募展は学割で無料だったり格安だったこともありよく見たものです。その頃には自分も出せればいいなと漠然と思っていたものでしたが、それが今ではなんとか美術会に所属するようにもなって、京都市美術館で見せる側になることができています。個展は経済的に少し余裕さあればだれでもできる行為ですが、京都市美術館の展示となるとそうはいきません。ある程度の規模の美術会に参加する、もしくは入選する必要があります。そのサイズも大きなものとなります。画材もさることながら気力も体力も必要になってきます。そこでは美術館に展示してもらうために作品を作ることが目的となり、もう採算など全く無視して自己満足のためだけにする行為ともいえるものです。ですから美術展への出品に値する作品とするにはお金も労力も伴います。好きだからこそ持続できるということでしょう。そうして創作にのめり込んだものが、作品として美術・芸術となっていくのだと感じます。最近でこそ美術によいやくと向かい合えるようになってきたと感じているのですが、いずれにしても生活につながらない行為ですので、そちらにのめり込もうにもそういう訳にいかないところがあります。これからも以前とは違うそれ以上のものを創作したと思う反面、さまざまな条件(経済的・社会的)の変化が影響してきます。以前の悩みはやや解決する方向には向かいながらも、また別の視点から思い悩む訳です。でもそうした創作でさまざまに思い悩んだ結果として少しづつ作品の表現には深みが出てきているようにも感じます。自身にとって絵を描くということは、いろんなことをしながらも描き続けることで、作品がその時々の体験などで、次第に深みが増すもののように感じます。